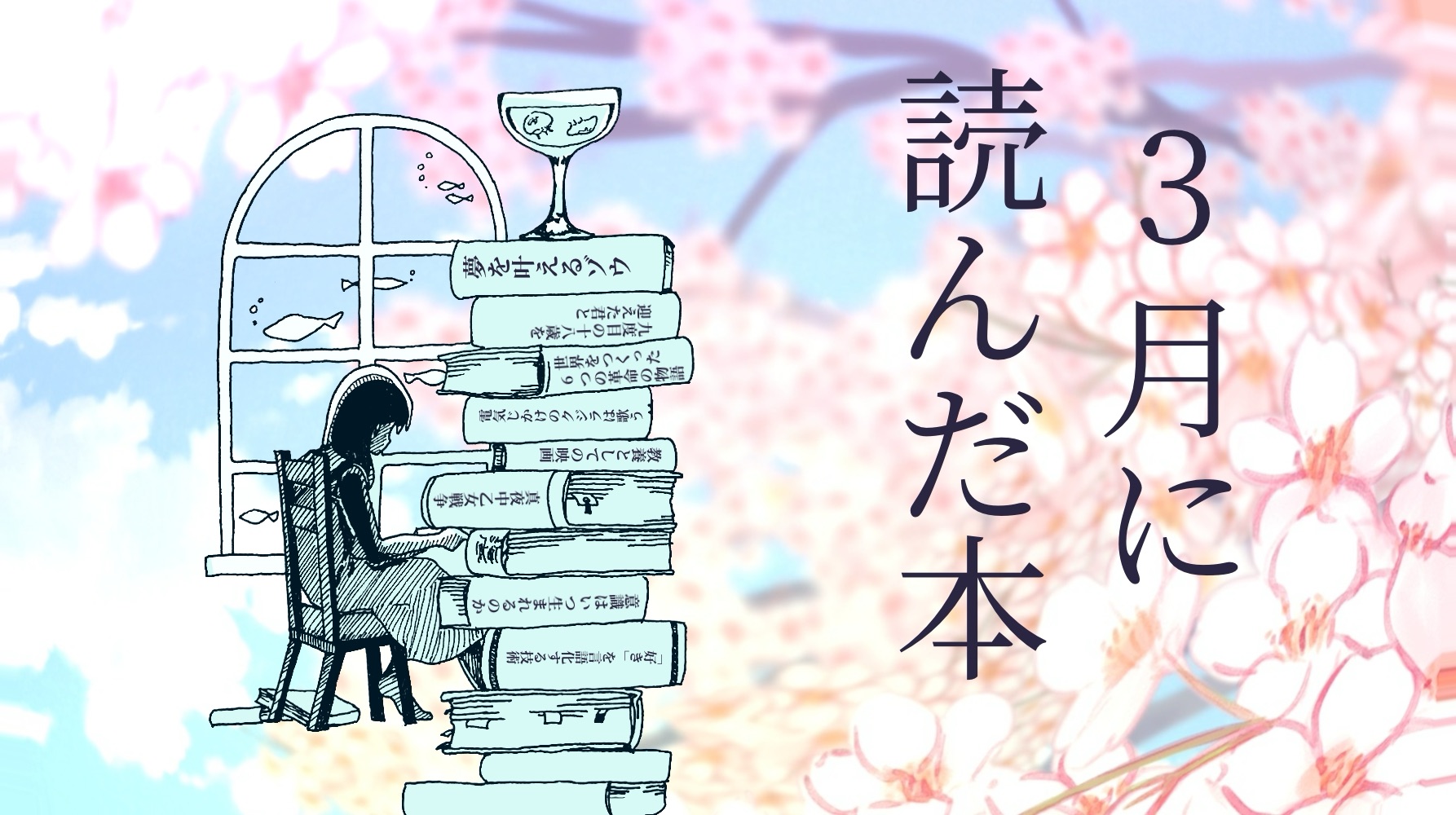君は花瓶になった
夢をかなえるゾウ1
水野敬也
知識を入れるだけではダメ。行動して経験しないと
やらずに後悔してることを今日始める
生き方なんて自分で選ぶもんや。自分が幸せだと感じることがらできれは、それでええんや。誰も努力なんて強制してへんで。そもそも、やらなあかんことなんて存在せんのや
自分が満たされてへんと、人を喜ばせることはでけへん。人に与えることがでけへんのや
九度目の十八歳を迎えた君と
浅倉秋成
みんなびしっと格好よくスーツを着ていたり、女の子もお洒落を楽しんだりして、本当に羨ましく思った。あぁいいな、って心の底から思った。でも口を開いてみれば、合言葉のように出てくるのは仕事の愚痴ばかり。みんな夢があったはずなのに、理想があったはずなのに、誰ひとりとして希望の仕事には就いていなかった。
私は別に夢が叶わないことが怖いんじゃないの。夢が叶わないことを受容する大人になってしまうことが怖いの。そうなってしまった私はたぶん、私の知る私ではない。そうなってしまったら私は、死んだも同然。そんなものには絶対になりたくないの。
年齢が変わらないというところにトリックとかはなく、本当に変わってないというSF設定をひとつのんで読み進めなくてはならない。高校時代の痛々しい恋愛の一人相撲が青春って感じがする。「大人になりたくない」という気持ちは私が常に抱えているものだったから、かなり心にくるものがあった。
意識はいつ生まれるのか
マルチェッロ・マッスィミーニ、ジュリオ・トノーニ
コンピュータで自分の脳が完全にコピーされたとしても、そのコンピュータ脳がなんらかの感情を本当に得ているのかはわからない。脳のコピーで永遠を得る契約は、本人じゃなくて、本人にいなくなって欲しくない周りの人が望むものかもしれないな。
情報を統合できるシステムがあるところに意識はある。脳と意識はひとりひとりのもので、他人の意識はわかちあえない。
電気じかけのクジラは歌う
逸木祐
自分が作る程度の曲は人工知能で簡単に作ることができるのに、それでも作る意味がどこにあるのだろうか。作る前からそんなことを考えて、作りはじめるところまでも行かない。
岡部さん。凡庸な人間は、演奏をしてはいけないと思いますか?
人工知能はあくまで優秀な伴走者。道具だった。人工知能は人間がイメージするものを簡単に形にできるという大きな力を持っているが、そもそものイメージはやはり人間が持っていなければならないという結論かな。
たくさんの人に聞かれないと仕事にはならないが、音楽は自分の楽しさのためにやったっていい。
「好き」を言語化する技術
三宅香帆
「好き」という感情は揺らいで消えやすいから、自分の言葉で気持ちを保存しておいた方がいい。写真やグッズはそれと同じ意図で集めている。
自分の感情をメモする前に他人の感想に触れると、そちらに引っ張られてしまう。
スラングができる理由は、俺とお前の間に説明なんかいらない、仲間だよな?同じ言語を使っている同志だよな?そんな暗黙の了解をとるため。
聞き手をどこに連れていきたいか意識して、反応を予測&緩急つける。
修正のクセをつける。
空欄の行が多くて読みやすいけど、思ったよりスカスカだなと思ってしまった。ブログみたいな感じで、伝えたいことを伝えるために書かれた文章で、この本の書き方そのものが、好きな物の言語化の良いやり方を体現している。
真夜中乙女戦争
F
「もっと恥を掻いておけばよかった」が刺さる。
主人公は先輩と黒服という2人の人物に影響を受ける。最後は東京タワーを燃やして終わる。ちょっとファイトクラブを感じた。
どうしようもない日々のつまらなさや無意味さ、周りの人がみんな馬鹿な猿に見える感覚、自分のことが好きではない感覚、青春が砂のように手から今もすり抜けていく焦りがわかるのが辛い。
東京タワーは都会の象徴っていうのがしっくり来る。
世界をつくった6つの革命の物語 新・人類進化史
スティーブン・ジョンソン
めちゃ面白かった。
ガラス、冷たさ、音、清潔、時間、光など、各分野でどうやって人間は発明をし、発展してきたかの歴史が語られている。
今までに積み重ねられてきた先人の知恵と、自分自身の新たな切り口(それは、その分野以外からの知識が多い)を加え、コップの水が溢れるように臨界点に達した時、新たな発明が起こる。ひとつの発明は、その目的のためだけでなく、他の誰かがその技術の別の使い方をして、ハチドリ効果的に世界が変わっていく。
仕事と人生に効く 教養としての映画
伊藤弘了
映画をただのエンタメだと信じて疑わないやつに、(本を突きつけて)この本が理解できるまで話しかけんな!理解できなかったなら、その本持って消えな!と叫んでやればよかったんだ。
映画を見ることはどれほど奥深くて、難しくて、教養がついて、面白くて、人生を豊かにするかを説明してあり、頭の中でずっとぼんやり思っていたことが言語化されていたようだった。自分の行動というか趣味を肯定して貰えた気がした。また、新たな視点や感想の書き方、面白そうな映画の紹介があり、今後観てみたい映画リストが増えてよかった。